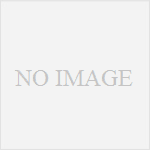その賃金はコストか投資か ―楠田 丘の「賃金とは何か」の示唆ー
賃上げ(量)が大きな関心事になっているが、賃金がコストまたは投資のどちらに沿ったものなのか(質)も極めて重要である。
一時勢いを増した欧米の成果主義賃金導入の社会的潮流とも調和しながら、まだ賃金体系が未整備であった幾つもの名だたる大手企業で、労使で職務の実態を公正・公平に調査しその体系化に奔走した代表的人物が楠田で、その自伝が標記の本である。
楠田は、欧米の成果主義賃金体系は、各種の職務に対して求人する、すなわち当該労働を買う「コスト」として成り立っており、往時の我が国では大概が終身雇用で、人の採用はすなわち「投資」であり、欧米の成果賃金を直に導入することはできないと論考した。我が国のそれは、一時の各人の業績(成果)に左右されず、各人の賃金はそれなりに上昇する投資(資産)の立場である。
楠田は、学歴(資源)や勤続年数(年功)を労働者の成果に取り入れ、職位(係長、課長、部長など)は成果の結果(昇進)であり、またその職位をこなすことが成果として賃金に反映させる構建で、終身雇用に成果を入れ込んだのだと私なりに推考した。
しかし、今や終身雇用の普遍性はなくなり、雇用のコスト化が進み、デトロイトの自動車産業に見るような厳しい労働市場になっている。かつて、トヨタを視察した米国の同業者たちは、欠勤した仲間を案じて自発的に対処する米国では見たことのない職場をみて、これでは勝てないと思ったそうである。非正規化・コスト削減の時勢ではあるが、労働への投資的施策は、産業保健にとっても極めて重要である。